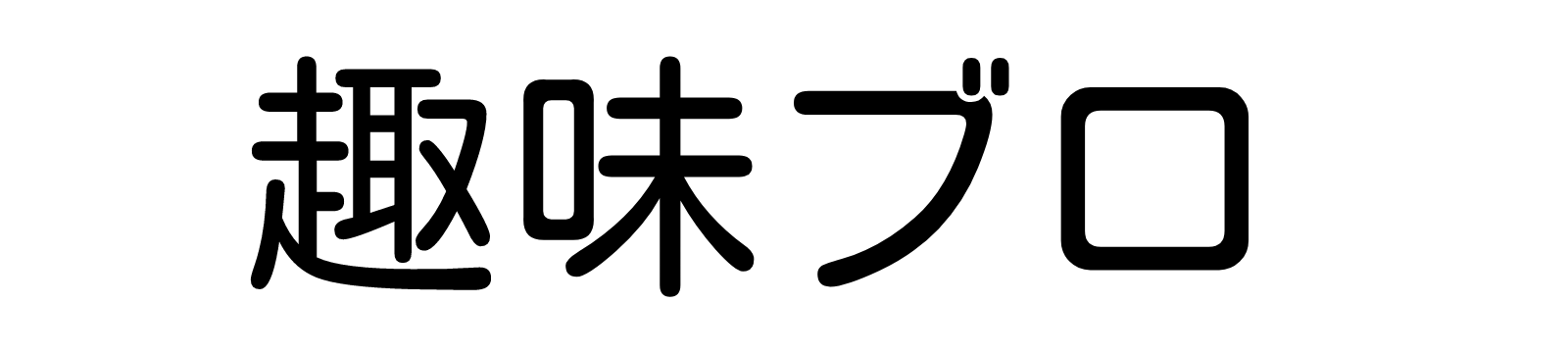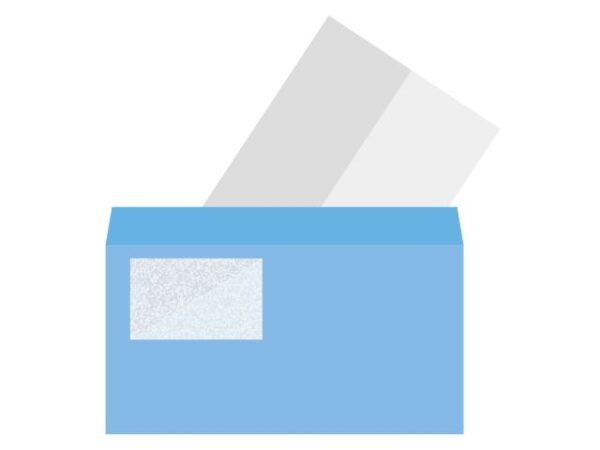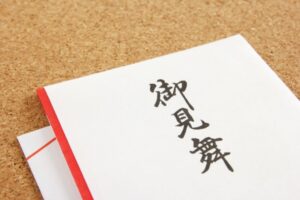大事な書類の送付に役立つ簡易書留、その使い方をご存知ですか?
私自身、履歴書を送る際に簡易書留を利用したことがあります。
その時は急いでいて、郵便局で手当たり次第に茶色い封筒を選び、宛名を書いて送った経験があります。
しかし、後になって、大切な書類を間違った方法で送ってしまったらどうしようと不安になったことがあります。
この記事では、簡易書留の基本的な使い方と書き方を簡潔に説明しています。
忙しい方は、目次から関心のある部分を読んで、すぐに理解することができます!
また、送り先に良い印象を与えたい方のために、適切な封筒の選び方と書き方も紹介しています。
ぜひこの記事を参考にして、簡易書留の正しい使い方を学び、大切な書類を安心して送りましょう。
簡易書留の基本は普通郵便と同様

簡易書留は普通郵便と同じくらい簡単ですが、いくつか留意すべき点があります。
簡易書留は重要な書類送付に適した方法
簡易書留とは、どんな目的で使用するのでしょうか?
書留は、郵便物の受け取りから配達までが記録される郵便サービスです。
全部で3種類の書留があります。
その中で、簡易書留は、郵便物が損害を受けたり、届かなかった場合に最大5万円まで保証されるものです。
書留の種類には、以下のようなものがあります。
- 一般書留:実際の損失額全額を保証
- 現金書留:現金の送付に特化した書留
- 簡易書留:損害補償は最大5万円までだが、一般書留より割安
簡易書留は、一般書留で送るほど高価ではないが重要な書類に最適です。
- 入学願書
- 履歴書
- 契約書
- 請求書
- 旅行券
- 招待状など
それぞれの特徴を理解し、用途に応じて適切に使用しましょう。
封筒表面の左下に「簡易書留」と赤色で明記する
簡易書留は通常の封筒で送ることが可能です。
もし「簡易書留」と書き忘れた場合でも心配はいりません。
郵便局で「簡易書留です」と伝えれば、スタンプを押してもらえます。
私は手書きが苦手なので、郵便局でスタンプを押してもらうことが多いです。
また、簡易書留用のスタンプも販売されていますので、きれいに仕上げたい方はスタンプを使ってみるのも良いでしょう。
郵便局を通じてのみ発送可能な簡易書留
簡易書留を発送する際には、必ず郵便局を経由する必要があります。
これは、重要な文書を扱うための措置です。
正式な手続きでは、郵便局のカウンターで「簡易書留をお願いします」と伝えることが求められます。
一般的に、郵便局の営業時間は平日の9時から17時ですが、平日に郵便局に行けない場合はどうすればよいでしょうか。
その際は、夜間や休日も対応するゆうゆう窓口を利用しましょう。
ゆうゆう窓口は、特別に設けられた窓口で、休日や夜間もサービスを提供しています。
ただし、利用できるサービスには制限があります。
営業時間は郵便局によって異なりますが、簡易書留の発送は可能です。
速達や普通郵便物の発送、切手販売、ゆうパックの発送なども取り扱っています。
最寄りのゆうゆう窓口の場所は、日本郵便の公式サイトで確認できます。
また、郵便局によっては簡易書留の手続きの際に「書留・特定記録郵便物等受領証」の記入を求められることがあります。
この場合、差出人の名前と住所を記入するだけで問題ありません。
追加料金を支払えば速達での簡易書留も可能
簡易書留は速達サービスの利用も可能です。
速達で送りたい場合は、郵便局の担当者に「簡易書留を速達で」と伝えるだけで手続きが完了します。
ただし、速達サービスを利用する場合、追加料金が発生するので注意が必要です。
速達料金は郵便物の重さに応じて変わります。
書留サービスの便利な特長
これまでに簡易書留の注意点を3つ挙げてきましたが、ここで書留サービスの便利な特長をいくつかご紹介します。
休日も配達される
通常の郵便は1月1日を除き、休日でも配達されます。
書留も、日曜日や祝日に配達されるサービスです。
休日に配達されるその他の郵便サービスには、速達、代引き便、配達日時指定郵便、ゆうパックなどがあります。
再配達サービス
受取人が不在の場合でも、当日の17時(※郵便局により異なる)までに再配達を依頼すれば、同日中の21時までに配達が可能です。
再配達の依頼は無料で、日時の指定もできます。
郵便追跡サービス
書留の受領証に記載された番号を用いて、郵便物の追跡ができます。
郵便料金計算サービス
郵便料金は、基本料金と運賃を合わせた金額で計算されます。
簡易書留の場合、これに簡易書留料金が加算されます。
簡易書留の追加料金は350円です(2024年1月現在)。
【簡易書留の料金計算式】
- 基本料金・運賃+350円=簡易書留の料金
基本料金は郵便物のサイズによって異なり、運賃は発送地から宛先までの距離で決まります。
日本郵便の公式サイトで郵便料金を計算することができますので、簡易書留を送る際の料金を事前に確認しておくと便利です。
簡易書留封筒の正しい書き方:表面と裏面のポイント

簡易書留でも、通常の郵便と同様に、封筒の書き方には基本的なルールが存在します。
では、封筒の表面と裏面にはどのように記入すれば良いのでしょうか?
縦書きと横書きの場合で、書き方にはどのような違いがあるのでしょうか。
このセクションでは、簡易書留封筒を縦書き、横書きそれぞれでどのように書くか、そのポイントを詳しく説明します。
重要な書類を送る際には、これらのポイントをしっかりと理解し、封筒に丁寧に記入しましょう。
封筒表面の正しい記入方法
封筒の表面には、受取人の氏名と住所を記入します。
封筒表面の記入ポイント(縦書き・横書き共通)
- 企業宛の場合は、「株式会社」などの正式名称を使用し「御中」を付ける
- 個人宛の場合、敬称は「様」を使用
- 番地やビル名は省略せずに記入
- 簡易書留の場合、左下に「簡易書留」と赤字で記入し、四角で囲む
封筒表面の記入ポイント(縦書き)
- 漢数字を使用することが推奨される
封筒表面の記入ポイント(横書き)
- 切手の位置は封筒を縦にした際、左上に配置
- 住所記入には数字を使用すること
会社の部署名や住所が長い場合は、先に相手の氏名を中央に記入すると見た目のバランスが取れます。
封筒裏面の適切な書き方
封筒の裏面には、差出人の氏名と住所を記入します。
郵便物に何らかの不備があった場合、差出人へ返送されるため、住所は正確に記入しましょう。
封筒裏面の記入ポイント(縦書き・横書き共通)
- 表記よりも小さい文字サイズで記入
- 封筒はのりで閉じる
- 敬称は不要
- 左上に発送日を記入
封筒裏面の記入ポイント(縦書き)
- 氏名と住所の記入方法には2種類がある
縦書き封筒では、①左半分に氏名と住所を全て記入する方法と、②右半分に住所を、左半分に氏名を記入する方法があります。
どちらの方法を採用しても問題ありません。
封筒裏面の記入ポイント(横書き)
- 差出人の住所と氏名を封筒の下部の1/3の範囲に収めるように記入する
簡易書留用封筒の選び方:文書ごとの最適なタイプは?

簡易書留を送る際には、封筒の選び方が重要です。
基本的には普通郵便と同じく、どんな封筒も使用可能ですが、内容物に適したサイズを選ぶことが肝心です。
特に大切な書類を送る際には、サイズが不適切で内容物が損傷するリスクを避けたいものです。
ここでは、異なる種類の文書に最適な封筒のタイプをご紹介します。
封筒の種類
- 長形封筒:縦が長い封筒(3種類)
- 角形封筒:大きなサイズの封筒(1種類)
- 洋形封筒:封入口がある封筒(1種類)
日本郵便局で取り扱っている封筒には、5種類あります。
【郵便局で販売されている封筒のサイズ】
- 角形2号(角2):240×332mm
- 長形3号(長3):120×235mm
- 長形40号(長40):90×225mm
- 長形4号(長4):90×205mm
- 洋形2号(洋2):162×114mm
履歴書や願書に最適な角形封筒
A4サイズの履歴書や願書を折らずに送りたい場合、角形2号が最適です。
ただし、大学などが特定の封筒の使用を指定している場合もあります。
自分で選ぶ際は、ビジネス文書に一般的な茶色の封筒ではなく、フォーマルな印象の白色の角形封筒を選ぶとよいでしょう。
納品書や請求書に適した長形封筒
納品書、請求書、手紙などを折って送る際には、長形封筒が便利です。
長形3号(長3)はA4サイズを三つ折りにするのに適しており、長形40号(長40)はA4サイズを四つ折りにするのに適した少し幅が狭いサイズです。
長形4号(長4)はB5サイズを三つ折りにする際に使用されます。
カード類に適した洋形封筒
招待状やカード類を送る際には、封入口がある洋形封筒が適しています。
郵便局で販売されている洋形2号(洋2)はハガキサイズの横型封筒で、こうしたアイテムに最適です。
どの封筒を使用する場合でも、簡易書留の書き方における基本的なポイントに従い、表面と裏面の書き方を適切に行うことが重要です。
封筒の選び方に加えて、書き方にも注意を払い、内容物と封筒を丁寧に扱いましょう。
簡易書留の正しい使い方と選び方をマスターしよう!
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 簡易書留の基本 | 普通郵便と同じ書き方で、重要文書に適した発送方法。 |
| 封筒表面の書き方 | 受取人の氏名、住所を記入。 企業宛は「御中」、個人宛は「様」を使用。 |
| 封筒裏面の書き方 | 差出人の氏名と住所を記入。 再配達の際に重要。 |
| 封筒の選び方 | 文書の種類に合わせて封筒を選ぶ。 角形、長形、洋形があり。 |
| 簡易書留の発送方法 | 郵便局を通じてのみ発送可能。 速達サービスの利用も可能。 |
この情報を元に、簡易書留の使い方を把握し、正確な書き方と適切な封筒の選び方を行いましょう。
大事な書類を安心して送るために、これらのポイントをしっかりと理解してください。