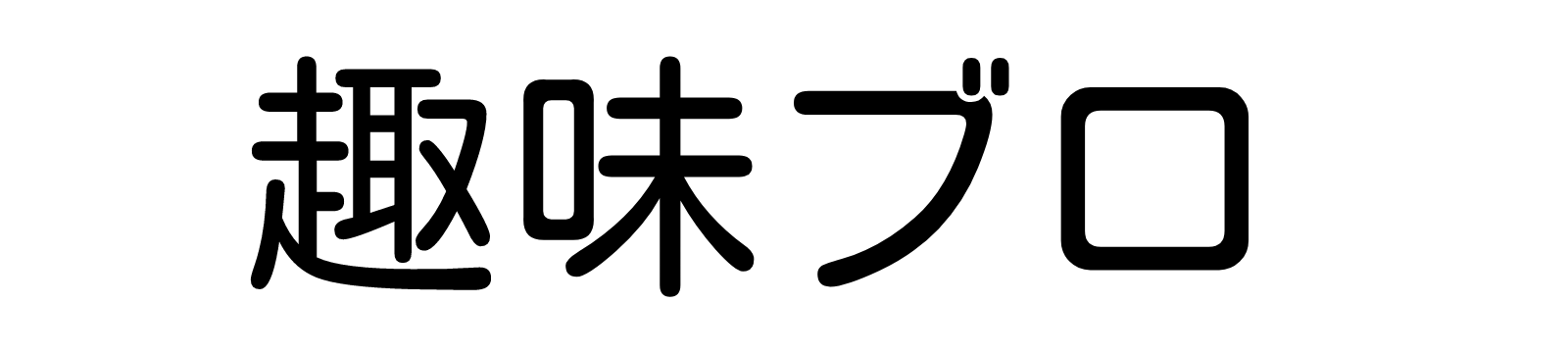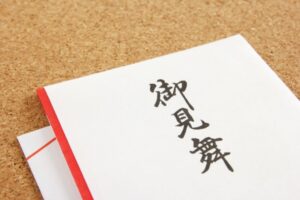土用の期間中、避けるべき行動を一覧にしてご紹介します。
土用の意義や、なぜこれらの行動を避けるべきかがはっきりしない方も多いでしょう。
万が一、土用期間中にタブーとされる行動をしてしまった場合の対処法も併せてお伝えします。
土用期間中に避けるべき行動一覧!

土用期間中に避けるべき行動のリストをお伝えする前に、まずは「土用って何?」という疑問に答えましょう。
旧暦は月の満ち欠けに基づいているため、季節感にズレが生じることがありました。
これを解消するため、中国から取り入れられた二十四節気や七十二候が用いられています。
二十四節気には立春や夏至、秋分などが含まれ、現在でも親しまれています。
しかし、日本独自の気候を反映するため「雑節」という概念が生まれました。
土用は、「立春」「立夏」「立秋」「立冬」の前の約18日間を指し、季節の変わり目を示します。
それでは、土用期間中に避けるべき行動について見ていきましょう。
土いじり、草むしり、井戸掘り、建築工事、地鎮祭
土用の時期は、土の神様が土中にいるとされ、この期間中は土に触れることが伝統的に避けられてきました。
土中で静かに過ごす土の神様は、土を動かす行為に不快感を示すと言われています。
したがって、以下のような「土動かし」行為は特に避けるべきです。
- 土を掘る、耕す
- 草を刈る、抜く
- 井戸や穴を掘る
- 建物の増築、改築、基礎工事
- 地鎮祭
これらは、土用の期間中に避けるべき行為とされています。
ただし、土用の期間は1年で約72日あり、これらの行為を完全に避けると生活に支障が出ることもあります。
そのため「間日」という、土の神様が天上に行くとされる日が設けられています(間日の意味とは?の章で詳しく解説)。
この日は「土動かし」を行ってもよいとされています。
旅行について
土用期間中、全方位が不吉とされるため、伝統的に旅行は避けるべきとされています。
これは土と直接的な関連はありませんが、不吉な時期に旅をすることは控えるべきだと言われています。
引っ越しに関する注意
土用の期間中の引っ越しも、旅行同様に避けるべきです。
特に「土用殺」と呼ばれる不吉な方位への移動は、避けるべきとされています。
土用の各季節における凶方位は、以下の通りです。
- 冬の土用:北東
- 春の土用:南東
- 夏の土用:南西
- 秋の土用:北西
新居購入のタイミング
新居購入も、土用期間中は控えるべきとされています。
季節の変わり目である土用は、心身のバランスが崩れやすい時期であり、新しいことを始める際にストレスや疲れが溜まりやすくなるためです。
就職や転職のタイミング
就職や転職も、環境の変化が大きいため、土用の時期は避けるべきとされています。
土用期間中は季節の変わり目であり、新しい環境への適応が難しくなることが考えられるからです。
結婚のタイミング
新しい生活を始める際は、より安定した時期を選ぶことが望ましいです。
開業のタイミング
開業は大きな挑戦ですが、土用の時期は体調を崩しやすいとされています。
土用の期間中に行ってしまった禁忌行為の対策

土用の期間中に、禁じられている行為をしてしまった場合の対策をお話しします。
たとえば「土用を忘れて土を触ってしまった」や「土用の期間に旅行計画を立ててしまった」といった場合、どうすればいいのでしょうか。
土をいじってしまった場合は、土に塩を撒き、お清めを行い、土公神に心から謝罪するのが良いでしょう。
ただし、土用に土をいじったからといって、必ずしも祟られるとは限りません。
昔の人々が、農作業を休むための期間として設けたという考えもあるので、過度な心配は不要です。
旅行に関しても同様です。
土用期間中に旅行を避けるべきとされていますが、やむを得ない事情があれば「この日しか調整できなかったことをお許しください」と土公神に謝罪するのが良い方法です。
土用期間中の土触れ禁忌の理由

では、なぜ土用の期間中に土に、触れることが避けられているのでしょうか。
土用の期間中、土中に土公神がいるとされていますが、土を司る神様が常に土中にいるわけではないという疑問もあります。
土用期間中が、特別視される理由を解説します。
土用の概念は、中国発祥の五行思想に由来します。
五行思想では、全ての物質が木、火、土、金、水の五つの元素から成り立っているとされます。
五行思想において、季節もこれらの元素に割り当てられます。
- 春は木の気
- 夏は火の気
- 秋は金の気
- 冬は水の気
しかし、この分類では土の気が季節として現れないため、各季節の変わり目、約18日間を土の気とすることで土用が設けられました。
したがって、土用期間中は一年で土の気が最も強くなる時期であり、土を触ることが土公神の不興を買うとされているのです。
間日の意味とは?

土用に関する話題の中で「間日(まび)」という言葉がよく出てきますが、これは一体何を意味するのでしょうか?
間日は、土公神が天界にいるとされる日を指します。
これは、土公神が土中から離れているため、土用期間中であっても土いじりをしても、祟りを受ける心配がない日ということです。
間日は、季節ごとに特定の日に設定されています。
- 春の土用:巳、午、酉の日
- 夏の土用:卯、辰、申の日
- 秋の土用:未、酉、亥の日
- 冬の土用:寅、卯、巳の日
これらは十二支に基づく伝統的な日の呼び方を、現代の暦に当てはめて設定されたものです。
縁起の良い土用の過ごし方

土用の時期を、縁起良く過ごす方法をご紹介します。
土用は季節の変わり目であり、体調を崩しやすい時期とされています。
そこで、この期間は日頃の疲れを癒す機会と捉え、家でゆったりと過ごすことがおすすめです。
また、土用の時期に特定の食材を摂ることが、縁起が良いとされています。
- 春土用:「い」のつく食べ物や白い食べ物
- 秋土用:「た」のつく食べ物や青い食べ物
- 冬土用:「ひ」のつく食べ物や赤い食べ物
家でリラックスしながら、体に良い食べ物を取り入れることで、健康と幸運を養うのが良いでしょう。
土用期間の過ごし方について知ろう
| 土用期間中の行動 | 土をいじるなどの行動は避け、万が一行ってしまった場合は塩を振ってお清めし謝罪する |
| 間日 | 土公神が天界に滞在する日で、土いじりが許される日 |
| 縁起の良い過ごし方 | 家でリラックスし、季節に応じた食材を摂取する |
このまとめは、土用期間中に避けるべき行動や、間日の意味、縁起の良い過ごし方について概説しています。
土用期間中は土を触ることを避け、万が一触れてしまった場合は適切に対処することが重要です。
また、間日は土いじりが許される特別な日であり、縁起の良い過ごし方としては、家でのんびり過ごし、季節に応じた食材を摂ることが推奨されています。