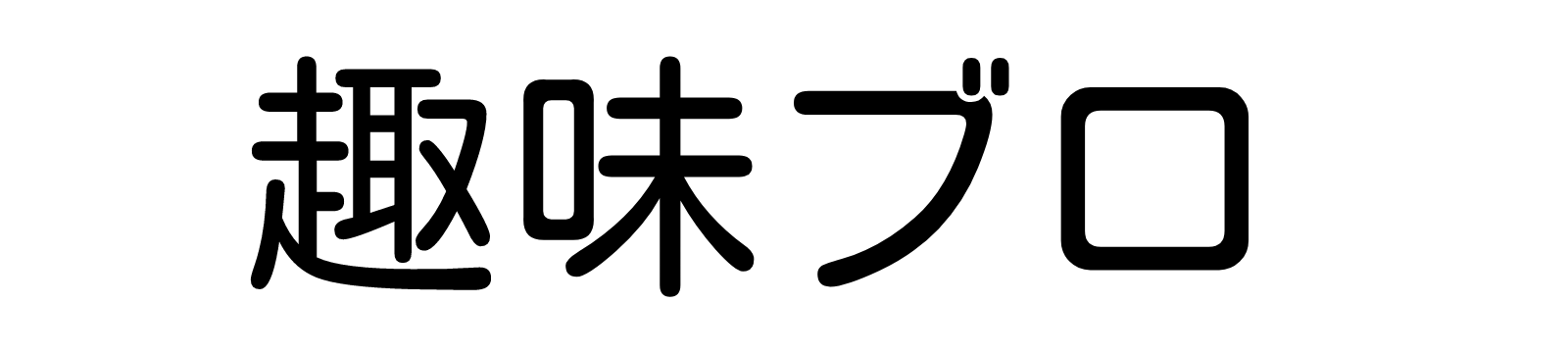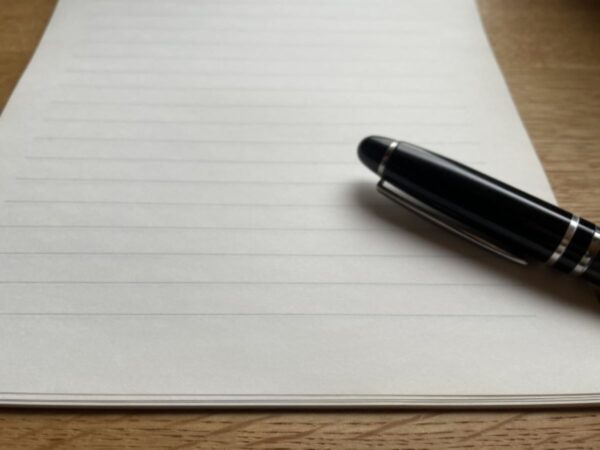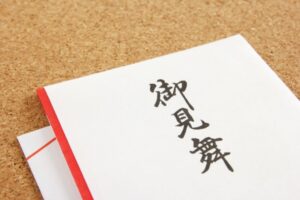追伸は、本文で述べ忘れた点を追加する際に役立つものです。
多くの人がこれを利用した経験があるかもしれませんね。
しかし、追伸をどこに配置すべきか正確に知っていますか?
署名の前か、それとも後か?
この記事では、追伸の適切な位置について、意外と知られていない事実を紹介します。
追伸を配置する正しい場所はどこ?
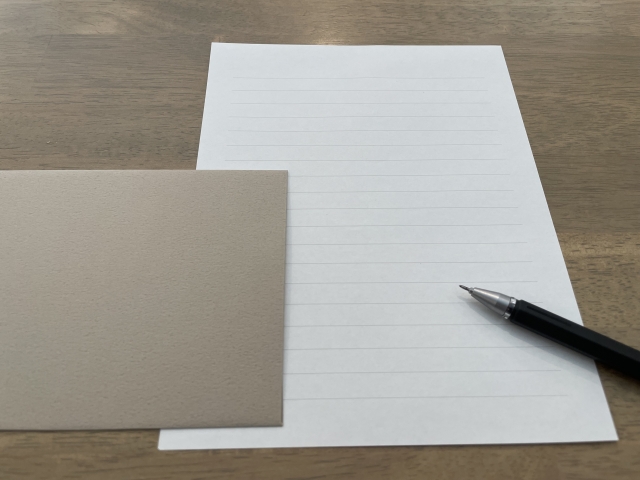
追伸は原則として、手紙やメールの終わりに記述されます。
しかし、手紙やメールを締めくくる際には、差出人の名前や組織名などが記載されることが一般的です。
その結果、追伸を差出人情報の前に置くべきか、後に置くべきかについて混乱する人もいます。
そこで、手紙・メール・葉書など、異なるコンテキストにおける追伸の適切な配置について紹介します。
追伸をどこに書くか?手紙編
縦書き手紙の場合
縦書きで書かれた手紙における追伸は、日付や差出人の情報、受取人の情報の後に配置されます。
追伸は手紙の構成要素の中で副次的な役割を果たします。
追伸を記述する際は、本文の終わりよりも少し下に位置させ、やや小さい字で書くことが一般的です。
内容は2、3行に留め、長くなりすぎないよう注意しましょう。
縦書き手紙で追伸を使用する際の注意点
- 上司や格式ある場合の手紙では、追伸の使用は避けるべきです。
追伸は「追加する」という意味合いを持ちます。
そのため、追伸を使用すると、「手間を省略した」と解釈され、礼儀に反することがあります。
上司への手紙や公式な内容の際は、面倒でも書き直すべきです。
縦書き手紙で追伸を使うのは、親しい人向けの手紙に限定しましょう。
横書き手紙の場合
横書き手紙においても、縦書きの場合と同じく、追伸は日付、差出人情報、宛名の後に置かれます。
横書き手紙は、縦書きに比べて公式な場では不向きであり、通常は親しい人へ送るものです。
そのため、横書き手紙で追伸を用いることは一般的です。
メールで追伸をどのように配置する?
メールでは、追伸は通常、本文終了後、署名の直前に配置されます。
メールが現代のビジネスコミュニケーションにおいて中心的な役割を果たしていることを考えると、追伸の正確な位置についてはよく検討されるべきです。
ビジネスメールにおける追伸の使い方には特に注意が必要です。
そのため、メールでは追伸を利用して本文とは異なる親切なメッセージや余談を伝える場合に限定することが推奨されます。
例:メールでの追伸
- 感謝の言葉を伝える際:「追伸 先週の会議でのご配慮、心より感謝申し上げます。」
- 最近の出来事を共有する場合:「追伸 お貸しした本、興味深く読んでいます。読了次第、感想をお伝えします。」
- 最近話題に上がったことに触れる際 :「追伸 お子様の学校行事は楽しめましたか? 次回、詳細を教えてください。」
- 今後の予定について言及する場合:「追伸 次回の集まりについて、ご意見を伺いたいです。」
- 思いやりのメッセージを送る際:「PS 近々の出張、安全にお過ごしください。」
追伸は必要に応じてのみ使用し、無理に加える必要はありません。
はがきにおける追伸の正しい位置
はがきでも、追伸は本文の後、最終的な署名や結びの言葉の前に挿入されます。
しかし、はがきでの追伸使用は、特に目上の人や公式の場では避けた方が良いとされています。これは、礼儀を欠く行為とみなされる可能性があるためです。
横書きのはがきは親しい人に対してのみ使用し、公式の場では縦書きを選択するのが適切です。
手紙やメールでの拝啓、敬具、追伸の使い方

社会人として、手紙やメールを適切に書く技術は非常に重要です。
特に、取引先や顧客への書簡では、不適切なフォーマットや言葉遣いが企業のイメージに悪影響を及ぼす可能性があります。
ここでは、手紙やメールにおける拝啓、敬具、追伸の配置と使用法について、実用的なガイドラインを提供します。
手紙の冒頭に「拝啓」を置くことの重要性と挨拶のマナー
正式な手紙では、最初の部分に「拝啓」という言葉を用いるのが慣例です。
これは手紙の開始を意味する頭語です。拝啓の直後には季節の挨拶や相手の健康を気遣う言葉を加えることが一般的です。
例えば、「新春の候、皆様の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。」や「年末の時節、ご家族皆様の健康と幸福をお祈りしております。」などが挨拶として適切です。
さらに、「拝啓」よりも更に敬意を表す言葉として「謹啓」があります。
「敬具」を手紙の締めくくりに使用する意義と、拝啓との関係
手紙を締めくくる際には、「敬具」を用いるのが通例です。
この言葉は、特にビジネスの場面でよく見られる結語です。「敬具」は「拝啓」と対をなす形で使われ、「拝啓」を頭語とした場合の結語は「敬具」となります。
頭語が「謹啓」である場合、結語は「敬白」となり、どちらも「敬意を表して」という意味合いを持ちます。
「かしこ」という女性専用の結語について
また、「敬具」や「敬白」とは異なり、女性が使用できる特有の結語として「かしこ」が存在します。
「かしこ」は、頭語が「拝啓」であれ「謹啓」であれ、適用可能ですが、通常は「一筆添えます」という頭語と組み合わせて使われます。「一筆添えます」と「かしこ」の組み合わせは、柔らかな印象の文面を作り出します。
女性が「拝啓」や「敬具」を使用することも可能ですが、「かしこ」を用いる選択肢もあることを覚えておくと良いでしょう。
手紙で「拝啓」と「敬具」を使用した際の追伸の位置について
手紙では、終わりの言葉としてよく「敬具」が用いられますが、その後に来る追伸の配置について疑問を持つ方もいるでしょう。
一般に、「敬具」は手紙の結びとして機能し、その直後に追伸を加えるのが慣例です。
追伸は本文の完了後、補足情報として追加されるもので、正式な終わりを告げる「敬具」の後に配置されます。
つまり、手紙の流れとしては、本文が終わり、「敬具」で締めくくられた後に追伸が続くことになります。
ビジネスの場面では追伸の使用を控えるべきとされています。その理由は、手紙や文書が計画的に、必要な情報を含めて書かれるべきだからです。
英語メールにおける追伸「P.S.」の配置と使い方
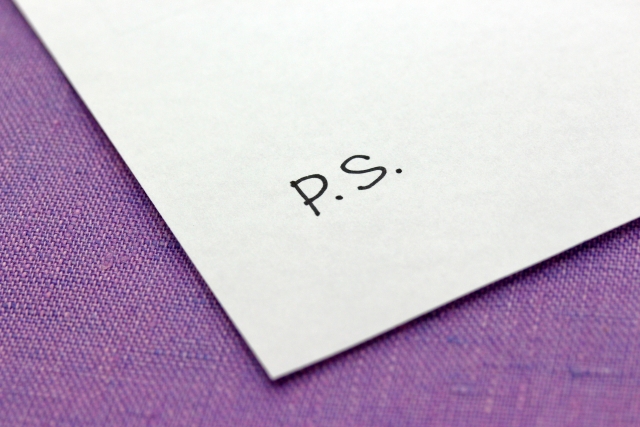
仕事上、英語でメールを送る機会がある人は多いでしょう。
英語の追伸は「P.S.」と表記され、これは広く知られています。しかし、「P.S.」の正しい使い方についてはどうでしょうか。
実際には、日本のビジネスメールにおけるマナーと同様、英語メールでも本文の最後に「P.S.」を用いて追加情報を記述します。英語圏でも、メールは再編集が可能なため、追伸を避けるのが一般的ですが、非公式なやり取りや親しい間柄では、追伸が用いられることがあります。
これは、主題とは異なるが共有したい特別なニュースや情報を伝える場合に特に見られます。
例えば、新しい仕事の開始、楽しみにしている新たな役職、そして来月の大きな引越しについての情報などです。
「P.S.」は親しい友人へのメッセージや、メールのやりとりで親密さを増すために使用されることがあります。この追記は、「もっと親しくなりたい」という願いも込められています。
海外の友人とのコミュニケーションでこの表現を使ってみるのも良いでしょう。
手紙とメールでの追伸を適切に使おう
| 追伸の位置 | 手紙では「敬具」の後、メールでは本文後に配置。ビジネス文書では追伸の使用を避けるべき。 |
| 英語メール | 「P.S.」を用いて追加情報を記述。親しい間柄や非公式なやりとりでは使用可。 |
| 追伸の意味 | 追伸は本文に関連しないが重要な情報や、相手との親密さを示すために用いられる。友人へのメールで効果的。 |
このまとめでは、手紙やメールでの追伸の正しい使用法と位置について解説しました。
手紙では「敬具」の後、メールでは本文の終了後に追伸を置き、ビジネス文書ではその使用を控えるべきです。
英語の「P.S.」は親しい人へのメールで相手との関係を深めるために役立ちます。